リハビリテーション部
「患者さんの立場で考える」という理念の下、患者さんのこころに寄り添ったリハビリテーションを
リハビリテーションを受けられる方の中には、突然の病気やケガによってこれまで当たり前に出来ていた活動や生活が不自由になってしまうことが少なくありません。事前の心の準備もないまま、これまでの自分自身とは異なった感覚、不自由な状態、将来への不安など様々な精神的ストレスを強いられています。当院リハビリテーション部では患者さんのこころに寄り添い、その失われた能力を最大限に回復出来るよう、精一杯取り組んでいます。
質の高いリハビリテーションの追求

リハビリテーション部
部長
寺坂 晋作
当院では中枢神経系疾患、運動器疾患、呼吸器疾患、心臓疾患やがんなど年間約3000名の患者さんのリハビリテーションを行っています。発症後すぐに開始する早期リハアプローチ、患者さんを中心に各専門職種が十分に連携をとったチームアプローチ、個々の疾患に専門的に対応する専門的アプローチ、訓練・治療時間を十分に確保するなど患者さんの回復が最大限になるよう、多面的にアプローチを行っています。
在籍する28名(理学療法士16名、作業療法士8名、言語聴覚士4名)のスタッフは、常に質の高いサービスが提供できるよう、学会発表や研修会参加、勉強会開催など日々そのリハビリテーション技術の研鑽に努めています。
- ■施設認定
- 脳血管疾患等リハビリテーション料(I)
- 運動器リハビリテーション料(I)
- 呼吸器リハビリテーション料(I)
- 心大血管疾患リハビリテーション料(I)
- がん患者リハビリテーション料
■診療実績
リハビリテーションセンターサイトに移動します。
疾患別リハビリテーションチームの特徴
脳・神経系リハビリテーション
- <対象となる疾患>
- 脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)、脳腫瘍、慢性硬膜下血腫、パーキンソン病、脳炎、髄膜炎、頭部外傷 など
脳卒中リハビリテーションでは、入院当日から開始する体制をとっており、PT(理学療法士)、OT(作業療法士)、ST(言語聴覚士)が医師・看護師と十分に連携を図り、積極的にアプローチすることで、『歩いて家に帰る』を目指しています。
特に、SCU(脳卒中ケアユニット)では、厳重なリスク管理のもと、合併症や廃用性障がいを極力抑え、365日体制で可及的早期から短期集中的なリハビリテーションを提供しています。その他の脳・神経疾患においても、各疾患の病態に応じたリハビリテーションを行っています。

理学療法では、起き上がりや立ち上がりなどの『基本動作』、歩行や階段などの『移動動作』に対して、発症前の動作・移動能力に回復することを目標に行います。

作業療法では、日常生活動作(食事、トイレ、歯磨き、顔や手洗い、着替え、風呂動作など)の改善を目的に、一緒に手を動かしたり、日常生活動作の練習を行っています。
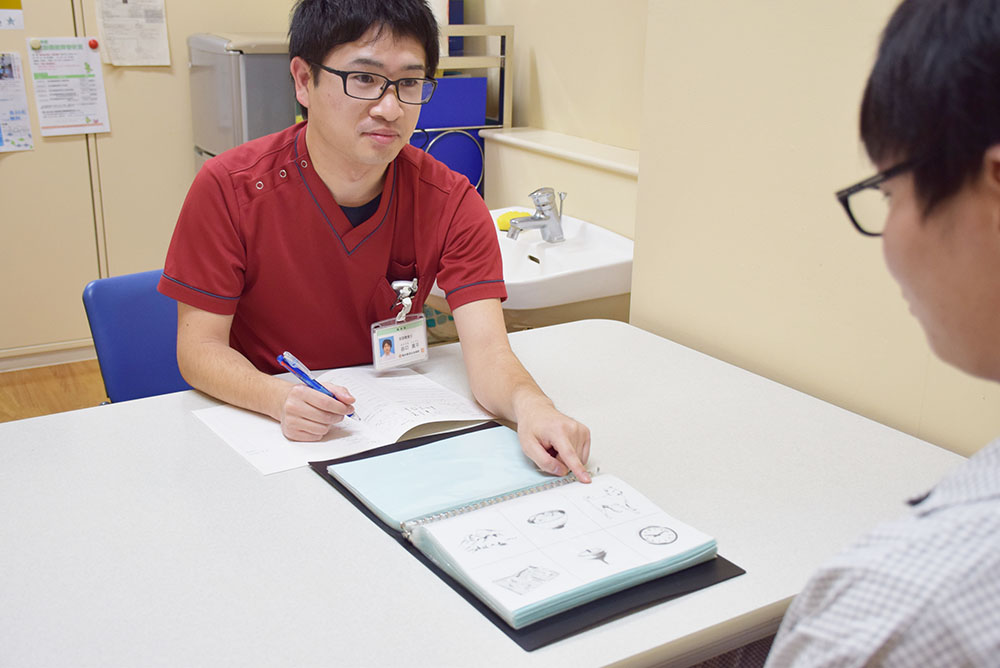
言語聴覚療法では、失語症(思いを言葉にすることが難しい、言葉の理解が出来ない)、構音障害(ろれつがまわりにくい)などと感じている方に対し、言語評価・訓練・指導を行い、日常生活上のコミュニケーション能力の向上を図っています。また、嚥下障害(水分や食物が飲み込めない)がある方に対して、安全に口から食べられることを目指し、他職種と連携しながらリハビリを行っています。
運動器リハビリテーション
- <対象となる疾患>
- 骨折、変形性関節症、脊椎疾患、筋・腱・靭帯損傷 など

低下した筋力の回復や関節可動域の改善を図り、起き上がり・立ち上がり・歩行などの基本動作の練習、階段の練習や更衣・排泄・食事などの日常生活動作の練習を行います。
骨折、人工関節、脊椎疾患などの手術後は早期から離床を開始し、合併症予防・機能向上を図ります。
~北陸有数の症例数 手の外科~
- <対象となる疾患>
- 手の外傷(骨折、腱断裂、神経損傷、切断)、関節疾患の方 など

北陸有数の症例数である手の外科では、手指の損傷具合や、手術の内容に合わせた関節可動域運動、筋力トレーニングなど、通常のリハビリテーションに加え、装具療法を中心とした治療を実施しています。装具に関しては手外科専門医と連携のもと、患者さんそれぞれの病態や手の形に合わせて装具を作製し、術後早期から「使用できる手」を目指しています。
呼吸リハビリテーション
- <対象となる疾患>
- 肺炎、気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、間質性肺炎、在宅酸素導入、肺切除や開腹手術の手術前後 など

呼吸状態に合わせた呼吸練習や運動により呼吸苦の軽減を図り、日常生活動作の獲得を目指します。手術適応の方には、術前から合併症予防のための取り組みや術翌日からの離床練習・排痰練習など早期からリハビリを実施しています。
心臓リハビリテーション
- <対象となる疾患>
- 急性心筋梗塞、狭心症(心臓カテーテル術後)、急性・慢性心不全 など

学会認定の心臓リハビリテーション指導士および認定理学療法士が、患者さんの体力に応じたプログラムを作成し、心電図や血圧をモニタリングしながら、適切な負荷をかけて運動療法をおこなっています。 また再発予防のための生活指導や栄養指導も、多職種と連携して実施しています。
2019年6月より心臓リハビリテーション外来を開設しました。運動療法を中心に医師の診察、看護師の生活指導など包括的に患者さんをサポートしています。ご希望の方はリハビリテーションセンターまでご相談ください。
吃音、音声障害のリハビリテーション
福井県内の病院ではほとんど行われていない吃音(言葉が「言いにくい」)や音声障害(声が「かすれる」「ふるえる」「出しにくい」)のリハビリを積極的に行っています。
吃音や音声障害などうまくしゃべることができないことによって、社会生活(地域、会社、学校、子ども園など)で困ることが多いです。
これらに対するリハビリは有効性が報告されています。本人・ご家族の悩みが少しでも軽減できるように発声の練習や日常生活のアドバイスを行っています。
対象は子どもから高齢の方まで幅広く実施しております。
がんのリハビリテーション
- <対象者>
- がんの治療(手術、抗がん剤治療、放射線治療)を受けられる方
がんによる痛みや食欲低下、だるさによって寝たきりになったり、がんの治療過程で身体機能が落ちたり、合併症を引き起こしたりすることがあります。それらを予防・改善し、治療効果を最大限に引きだすことを目的にリハビリテーションを行っています。
手術を受ける際は、事前に外来でリハビリスタッフが介入し、運動指導や不安の軽減に努めています。治療による状態の変化に応じて、医師や看護師など多職種が連携を図りながら、よりよい日常生活を送れるようにサポートしていきます。
また近年の研究により、がんの治療中、治療後に適正な運動を行うことで、代謝や免疫機能の活性化、精神的ストレスの緩和などによって、QOL(生活の質)が高められることが分かってきています。
院内医療チームへの参画
カンファレンスの参加や、各種教室での指導など、質の高い医療を実現する為、他の専門職と十分に連携をとりながらチーム医療に取り組んでいます。
- ・脳卒中チーム
- ・整形外科チーム
- ・呼吸サポートチーム
- ・心臓リハビリテーションチーム
- ・肝臓病チーム
- ・糖尿病チーム
- ・嚥下チーム
- ・褥瘡対策チーム
- ・認知症ケアチーム
スタッフの認定資格
-
認定理学療法士
4名
-
心臓リハビリテーション指導士
3名
-
3学会合同呼吸療法認定士
4名
-
糖尿病療養指導士
2名
-
日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー
1名
-
健康運動指導士
1名
-
日本褥瘡学会認定褥瘡理学療法士
1名
-
DMAT災害派遣医療チーム隊員
1名
-
骨粗鬆症マネージャー
2名